「投資の勉強しても、次の日には忘れてる…」
そんな悩み、ありませんか?
実は私も5年前まで、まったく同じでした。
本を読んでも、セミナーに参加しても、気づけば元の自分に戻ってる。
情報は散らかり放題で、「あの記事、どこに書いたっけ?」と探すだけで時間が溶けていく日々。
でも、あることをきっかけに、学習スタイルを根本から変えてみたんです。
それが「デジタルノート」の活用でした。
今では日経新聞の記事も、企業情報も、投資アイデアも、すべて3秒で検索可能。
過去の自分の考えもすぐに振り返れて、投資判断のスピードが劇的に変わりました。
今日は、そんな私の「知識投資術」を、包み隠さずお伝えします。
学び直しの一歩、一緒に踏み出しませんか?
この記事の読みどころ
✅️学習効率が劇的に向上するデジタルノート活用法を、実体験をもとに具体的にご紹介します
✅️投資判断に必要な情報整理術として、経済ニュースや企業情報をどう記録・活用するかがわかります
✅️先延ばし癖を克服する仕組みづくりのヒントが手に入り、学び直しへの一歩が踏み出せます
✅️日経新聞の読み方が変わるデジタルツールとの組み合わせで、難解な経済用語も自分のものにできます
✅️お金を稼ぐ力に直結する学習法が身につき、将来的な資産形成への道筋が見えてきます
なぜ「紙のノート」では記憶に残らなかったのか
情報が散らばる恐怖
以前の私は、A4ノートに手書きで学習内容を書き留めてました。
セミナーのメモはこのノート、読書メモは別のノート、投資アイデアはまた別のノート…。
気づけば本棚には10冊以上のノートが並び、「あの情報、どこに書いたっけ?」と探す時間だけで10分、15分が過ぎていく。
これ、めちゃくちゃもったいないですよね。
特に投資の世界では、スピードが命です。
ある企業の過去の業績推移を確認したいとき、以前読んだアナリストレポートの要点を思い出したいとき、「あのノートのどこかに書いたはず…」では、チャンスを逃してしまいます。
記憶の「検索性」という盲点
人間の脳は、情報を「関連付け」して記憶する仕組みになってます。
でも紙のノートは、基本的に「時系列」でしか情報が並べられません。
2023年3月に書いた内容と、2024年8月に書いた内容を一緒に見比べることは、物理的に難しいんです。
デジタルノートの最大の強みは、この「検索性」と「関連性」にあります。
キーワードで一瞬にして情報を引き出せるだけでなく、タグ機能やリンク機能を使えば、バラバラの時期に書いた内容同士を瞬時につなげられるんです。
私のデジタルノート活用術──3つの柱
【柱1】日経新聞の「気になる記事」即座にストック
毎朝の日課は、日経新聞電子版のチェックです。
以前は「ふーん、そうなんや」と読んで終わりやったんですが、今は違います。
気になった記事は、デジタルノートアプリに即座に保存。
私が使ってるのは「Notion(ノーション)」という無料アプリですが、「Evernote(エバーノート)」や「Microsoft OneNote(マイクロソフトワンノート)」でも同じことができます。
具体的な手順はこんな感じ:
- 日経新聞電子版で記事を読む
- 興味深い内容なら、記事URLをコピー
- Notionの「経済ニュースデータベース」にペースト
- 記事タイトル、日付、関連企業名、キーワードを入力
- 自分の感想や考察を3〜5行でメモ
この最後の「自分の感想」が超重要なんです。
なぜなら、人は「自分の言葉で説明したこと」しか本当の意味で理解できないんです。
例えば、先日「日本銀行が金融政策を変更」というニュースがありました。
私はこんな風にメモしました:
私の考察: 金利が上がると、借金してる企業は返済負担が増える。でも預金者にとってはプラス。不動産市場への影響も大きそう。REITの動きをチェックしたい。住宅ローン金利との関係も調べる。
このメモのおかげで、後日「REIT」や「住宅ローン」で検索したときに、この記事が引っかかってくれるわけです。
関連性が生まれるんですね。
【柱2】企業研究ノートで投資判断の質を上げる
投資をする上で、企業研究は欠かせません。
でも、決算書を読んでも、IRページを見ても、「で、結局この会社どうなん?」って迷うことありますよね。
私はデジタルノートに、企業ごとのページを作ってます。
まるで「自分だけの会社図鑑」です。
企業ページに記録する項目:
- 基本情報: 業種、設立年、本社所在地、社長名
- ビジネスモデル: どうやって稼いでるか?競合は?強みは?
- 財務データ: 売上高、営業利益率、ROE、自己資本比率の推移
- 投資判断メモ: 買いたい理由、懸念点、目標株価
- ニュースクリップ: 関連する日経記事のリンク集
- 自分の考察: なぜこの会社に注目してるのか
例えば、私が注目してる「トヨタ自動車」のページには、EV戦略の記事、決算発表の要点、アナリストレポートの引用、そして「中国市場でのシェア低下が気になる。でも北米は堅調。全固体電池への投資が鍵」みたいな自分の考察が並んでます。
これを続けることで、数ヶ月後に「トヨタの株価が動いた!」というニュースを見たとき、即座に過去の自分の分析と照らし合わせられるんです。
「あ、やっぱり全固体電池のニュースやったか」とか「中国市場の懸念が現実になったな」とか。
この「答え合わせ」ができるのが、デジタルノートの醍醐味です。
そして何より、自分の予測が当たったときの喜びは、学習意欲をめちゃくちゃ高めてくれます。
【柱3】用語集で「わからない」を「わかる」に変換
日経新聞を読んでると、「ROE」「PER」「TOPIX」「量的緩和」みたいな専門用語が山ほど出てきますよね。
その都度スマホで検索して、「ふーん」で終わらせてませんか?
私は、わからない言葉に出会うたびに、デジタルノートの「経済用語集」に追加してます。
しかも、ただ意味を書くだけやなくて、「自分なりの理解」を記録するんです。
例:ROE(自己資本利益率)の私の解説
ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
簡単に言うと「株主が出したお金で、どれだけ効率よく利益を生み出せてるか」の指標。ROEが高い = 少ない資本で大きく稼げてる = 経営効率がいいってこと。
日本企業の平均は8〜10%くらいやけど、アメリカの優良企業は15〜20%あったりする。投資先を選ぶときの重要な目安の一つ。
注意点: 借金を増やしてもROEは上がるから、自己資本比率とセットで見なあかん!
このページに、関連する日経記事のリンクも貼っておきます。
すると、「ROE」で検索したときに、用語の意味だけじゃなくて、実際の企業分析の事例も一緒に出てくるわけです。
3ヶ月もすれば、自分だけの「経済用語辞典」が完成します。
そしてこれが、日経新聞をスラスラ読めるようになる秘訣なんです。
デジタルノートが「学習の質」を変えた3つの理由
理由1:「思い出す」から「探し出す」へのシフト
人間の記憶力には限界があります。
でも、デジタルノートは忘れません。
私が意識してるのは、「覚えようとしない」こと。
その代わり、「いつでも探し出せる仕組み」を作る。
これが、デジタル時代の新しい学習法やと思うんです。
大事なのは「記憶」することではなくて、「理解」すること。
そして「必要なときに引き出せる」こと。
デジタルノートは、その理想を叶えてくれます。
理由2:「振り返り」が習慣になる
紙のノートって、書いたら終わり、ってなりがちですよね。
でもデジタルノートなら、過去の記録を見返すのが本当に楽なんです。
私は毎月末に「振り返りタイム」を設けてます。
その月に記録した企業情報を見直したり、自分の投資判断が当たったか外れたかを確認したり。
この振り返りが、次の学びにつながります。
「あ、この考え方は甘かったな」「この視点は良かった!次も使おう」って。
投資の世界では、「経験から学ぶ」ことが成長の鍵です。
でも経験って、記録しておかないと、記憶の中で美化されたり、逆に忘れ去られたりします。
デジタルノートは、正直な「過去の自分」を保存してくれる、優秀なパートナーなんです。
理由3:「知識の複利効果」が働く
複利って、投資でよく出てくる概念ですよね。
元本に利息がついて、その利息にまた利息がついて…という雪だるま式の成長。
実は、学習にも同じことが言えるんです。
デジタルノートに情報を蓄積し続けると、新しい知識が既存の知識と結びついて、理解が「加速度的に」深まっていきます。
例えば、私が最初に「ROE」を学んだとき、それは単なる一つの指標でした。
でも、その後「自己資本比率」を学び、「PBR(株価純資産倍率)」を学び、「バフェットの投資哲学」を学ぶうちに、それらがすべて「ROE」という軸でつながっていることに気づいたんです。
この「知識のネットワーク化」こそが、デジタルノートがもたらす最大の恩恵やと思います。
具体的にどうやって始める?ステップバイステップガイド
ステップ1:ツールを選ぶ(無料で十分!)
まず、デジタルノートアプリを一つ選びましょう。
私のおすすめは以下の3つ:
- Notion(ノーション):
データベース機能が強力。企業情報の管理に最適。無料プランで十分使えます。 - Evernote(エバーノート):
クリッピング機能が便利。ウェブ記事の保存が簡単。こちらも基本無料。 - Microsoft OneNote(マイクロソフトワンノート):
本文のレイアウトの自由度が高い。ページの階層構造で情報を整理でき、完全無料。
どれを選んでも大丈夫。
大事なのは「一つに決めて、使い続けること」です。
ステップ2:最初は「気になった記事を3つだけ」保存
いきなり完璧を目指すと、続きません。
まずは、日経新聞や経済ニュースサイトで「へぇ、面白いな」と思った記事を、3つだけノートに保存してみてください。
記事のURLと、一言感想を添えるだけでOK。
「量的緩和ってこういうことか。預金金利への影響が気になる」みたいな感じで。
ステップ3:週に一度、5分だけ振り返る
週末に、その週保存した記事を見返してみましょう。
「そういえばこんなニュースあったな」「この企業、その後どうなってるかな?」って。
この5分間の振り返りが、学習を定着させる鍵です。
ステップ4:気になる企業のページを作る
慣れてきたら、「この会社、ちょっと面白そう」と思った企業のページを作ってみましょう。
最初は、会社のホームページから基本情報をコピペするだけでも十分。
そこに、日経新聞の関連記事を少しずつ追加していく。
3ヶ月もすれば、立派な「自分だけの企業研究ノート」が完成してます。
ステップ5:用語集を充実させる
新しい経済用語に出会ったら、その場でスマホの辞書で調べて、デジタルノートに保存。
このとき、「自分の言葉で言い換える」のを忘れずに。
「量的緩和 = 日銀がお金をジャブジャブ市場に流すこと。金利を下げて、企業がお金を借りやすくする政策」みたいな感じです。
先延ばし癖を克服する「小さな習慣」のコツ
「完璧主義」を捨てる
デジタルノートの最大の敵は「完璧主義」です。
「ちゃんとしたノートを作らなきゃ」って思うと、結局何も書けなくなります。
私も最初はそうでした。
でも、今は「とりあえず保存」「とりあえずメモ」を合言葉にしてます。
後から整理すればいいんです。
「1日3分」から始める
学習習慣って、小さく始めることが大事。
朝のコーヒータイムに、日経新聞の見出しをチェックして、気になった記事を1つだけノートに保存する。
たったこれだけ。
3分でできることなら、続けられますよね。
「検索して喜ぶ」を楽しむ
デジタルノートの真価は、「検索」にあります。
ちょっとした疑問が浮かんだとき、自分のノートを検索してみてください。
「あ、これ前に調べたことあるやん!」って気づく瞬間、めちゃくちゃ嬉しいですよ。
この小さな成功体験が、学習意欲を持続させてくれます。
投資の世界で「学び続ける人」が勝つ理由
市場は常に変化している
株式市場は、生き物です。
昨日の常識が、今日は通用しません。
だからこそ、学び続けることが大事なんです。
デジタルノートは、この「変化」を追いかけるのに最適なツールです。
過去の分析と現在の状況を比較することで、「何が変わったのか」「なぜ変わったのか」が見えてきます。
情報の「質」が投資成績を左右する
投資で成功するには、「誰よりも早く」じゃなくて「誰よりも深く」理解することが大切やと、私は思います。
表面的なニュースに飛びつくのではなくて、「このニュースの背景には何があるのか」「長期的にどんな影響があるのか」を考える。
その思考のプロセスを、デジタルノートに記録していく。
これが、投資判断の「質」を高める秘訣です。
「自分の頭で考える力」が財産になる
投資の世界には、いろんな情報があふれてます。
アナリストの予測、投資顧問の推奨、SNSの噂話…。
でも、最終的に判断するのは自分自身です。
そのとき、過去の自分の思考プロセスが記録されてるデジタルノートは、最高の相談相手になります。
「前回こういう判断をして失敗した。今回は違うアプローチを試そう」
「この考え方は過去にうまくいった。今回も応用できるかも」。
この「自分との対話」こそが、投資家としての成長を加速させます。
「学ぶ楽しさ」を再発見した私の変化
日経新聞が「宝の山」に見えてきた
以前は「難しい」「面倒くさい」と思ってた日経新聞が、今では「宝の山」に見えます。
一つ一つの記事が、投資のヒントであり、ビジネスのアイデアであり、世の中の流れを読む手がかりです。
デジタルノートに記録していくことで、バラバラだった情報が「つながる」感覚を味わえます。
「わからない」が怖くなくなった
以前は、知らない言葉に出会うと、「自分はまだまだやな…」って落ち込んでました。
でも今は違います。
「お、新しい言葉発見!ノートに追加しよ」って、むしろワクワクします。
知らないことは、恥ずかしいことではなくて、成長のチャンスって思えるようになりました。
投資が「ギャンブル」から「戦略」に変わった
デジタルノートで学びを蓄積してきた結果、投資に対する姿勢が大きく変わりました。
以前は、「なんとなくこの株上がりそう」みたいな感覚で投資してました。
でも今は、「この企業の強みはここで、業界の成長率はこれくらいで、だからこの株価水準なら買い」みたいに、根拠を持って判断できるようになりました。
もちろん、すべてが当たるわけではありません。
でも、負けたときも「なぜ負けたのか」を分析できるので、次につながります。
プロの知恵を借りる大切さ──私の「学びの師匠」
ここまで、デジタルノートを使った「自分なりの学習法」をお伝えしてきました。
でも正直に言うと、私も最初から一人でできたわけではありません。
学びの過程で、何人もの「師匠」に助けられてきました。
書籍、セミナー、そして何より、「経験豊富な投資家の知恵」です。
実は私、「株歴50年超の熟練投資家、藤ノ井俊樹氏の推奨銘柄情報『旬の厳選10銘柄』」というレポートを、定期的に参考にさせてもらってます。
このレポート、ただの「推奨銘柄リスト」ではないんです。
藤ノ井さんご本人が、「なぜ今この株を買いとするのか」その根拠を、動画や資料で詳しく解説してくれるんです。
プロの視点が「学びの質」を変える
自分なりに企業研究をするのも大事。
でも、50年以上も投資の世界で生き抜いてきた方の視点を学ぶことで、「ああ、そういう見方もあるんや!」っていう新しい発見がたくさんあります。
例えば、私が「この企業の売上成長率すごい!買いやな」と思ってても、藤ノ井さんのレポートを見ると「でも営業利益率が下がってきてるから注意が必要」みたいな指摘があったり。
この「プロの視点」を、自分のデジタルノートに取り込んでいくことで、投資判断の精度がグンと上がりました。
初心者こそプロの知恵を借りるべき
「投資なんてやったことない」「経済新聞読んでもわからない言葉だらけ」
そんな方こそ、プロの知恵を借りることをおすすめします。
藤ノ井さんのレポートは、「経験の浅いビギナーでも活用できる」ように作られてます。
上値下値の目処など、具体的な戦略も示されてるので、「じゃあ自分はどう動けばいいのか」が明確になるんです。
もちろん、投資判断は最終的に自己責任です。
でも、「何も知らない状態」で市場に飛び込むのと、「プロの視点を学んだ上で」挑戦するのとでは、成功確率が全然違います。
興味がある方は、ぜひ一度チェックしてみてください:株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄
『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!
![]()
私自身、このレポートで学んだ内容を、デジタルノートにしっかり記録して、自分の知識として定着させてきました。
プロの知恵 × デジタルノートの組み合わせ、本当に最強です。
ユーザーの声「年間利益は平均して300万円くらいです」
投資顧問が自信を持ってお届けする推奨10銘柄
![]()
最後に:あなたの「学び直し」を応援しています
今、日本では「リスキリング(学び直し)」という言葉が注目されてます。
年齢に関係なく、新しいスキルや知識を身につけて、人生を豊かにしていこうという動きです。
特に投資の世界は、学べば学ぶほど、可能性が広がる分野です。
「もう遅い」なんてことは、絶対にありません。
私も30代になってから、本格的にデジタルノート活用を始めました。
それまでの何年間も、情報を散らかしたまま、記憶に頼ってばかりでした。
でも、変わろうと決めて、小さな一歩を踏み出したことで、確実に人生が変わりました。
あなたも、今日から始めてみませんか?
「でも、一人で始めるのは不安…」そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
特に初心者の方こそ、経験豊富な投資家の視点を学ぶことで、遠回りせずに済みます。
もしあなたが「本気で投資を学びたい」「資産形成の第一歩を踏み出したい」と思うなら、株歴50年超のプロによる推奨銘柄!
![]() をチェックしてみてください。
をチェックしてみてください。
この記事が、あなたの「学び直し」のきっかけになれば、こんなに嬉しいことはありません。
日経新聞を開くたびに、「これ、ノートに保存しとこ!」ってワクワクする。
わからない言葉に出会うたびに、「お、新しい知識ゲット!」って喜ぶ。
そんな「学ぶ楽しさ」を、一緒に味わいましょう。
あなたの「学び直し」が、素敵な未来につながりますように。
【補足】私が実際に使ってるデジタルノートの構成
最後に、参考までに、私のNotionノートの構成をご紹介します。
1. 経済ニュースデータベース
- 日経新聞の気になる記事をストック
- タグ:金融政策、企業決算、業界動向、海外経済など
- 検索用キーワードも入力
2. 企業研究ノート
- 気になる企業ごとにページを作成
- 財務データ、ビジネスモデル、投資判断メモ
- 関連ニュースのリンク集
3. 経済用語集
- わからなかった言葉を自分の言葉で解説
- 関連記事へのリンクも追加
4. 投資日記
- 自分の投資判断とその理由を記録
- 結果の振り返りと反省点
5. 学習メモ
- 読んだ本の要点
- セミナーで学んだこと
- プロのレポート(藤ノ井さんのレポートなど)の要点
6. 月次振り返り
- その月の学びのまとめ
- 次月の学習テーマ設定
この6つの柱で、私の「学びのデータベース」は成り立ってます。
あなたも、自分なりの構成を見つけてみてください。
正解はありません。
大事なのは、「続けられる仕組み」を作ることです。


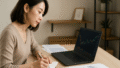

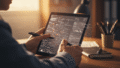

コメント