「円安」という追い風がなくなっても成長できる企業とは?
トランプ次期大統領の関税政策という向かい風が吹く中、日本企業はどう舵を切るのか——。
日立建機の最新決算発表は、日本企業が直面する課題と挑戦が凝縮された一枚の見取り図です。
多くの方が「難しそう」と敬遠しがちな経済ニュースですが、実はあなたの資産形成や投資判断に直結する重要なヒントが隠されています。
「円安効果の剥落」「地政学リスク」「真の競争力」。
これらのキーワードを理解するだけで、あなたの投資の視点は大きく変わるでしょう。
今回は日立建機の業績予想を通じて、経済ニュースの「本当の読み方」と「投資に活かすコツ」をわかりやすく解説します。
日経新聞を読みこなせば、あなたも「お金を育てる目」を手に入れられるのです。
この記事の読みどころ
✅️日立建機の26年3月期業績予想から読み解く日本企業の世界戦略
✅️次期トランプ政権による関税の影響はすでに300億円と試算済み
✅️欧州市場の回復と中国の大型ショベル需要増加が成長のカギに
✅️円安効果が剥落しても増益を実現するための戦略とは
✅️建機業界の動向から見えてくる世界経済の今後と投資のヒント
⚡ ニュースの要点:3行でザックリまとめ

- 日立建機は26年3月期の純利益を前期比2%増の830億円と予想
- 円安の効果は剥落するが、建機販売台数増加で増益を目指す
- トランプ次期政権による関税の影響額は約300億円と試算済み(業績予想には未反映)
🔍 ニュースの基本情報:5W1Hで深掘り!
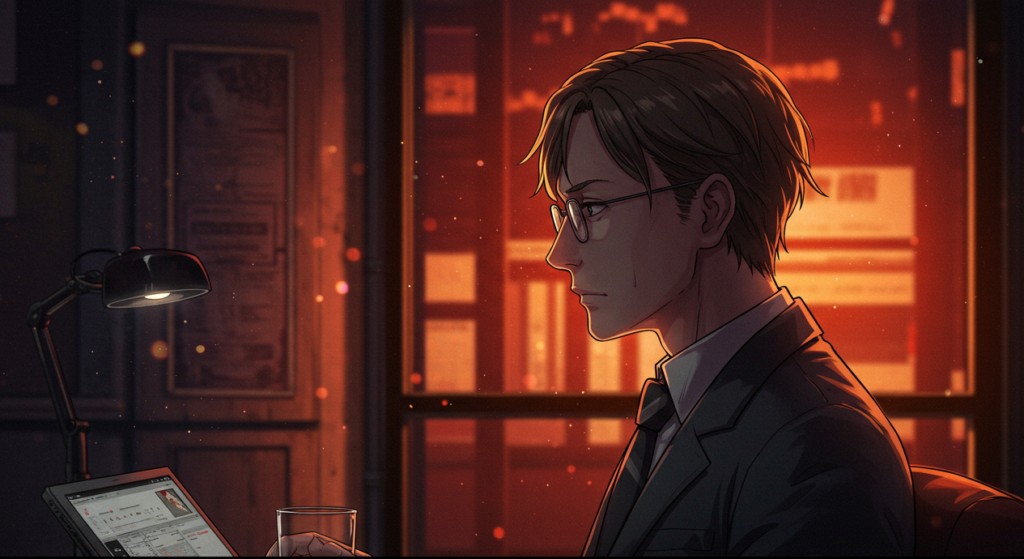
🤷🏻♀️What(何が起きたのか)
日立建機が2026年3月期の連結純利益を前期比2%増の830億円と予想しました。
調整後営業利益は4%増の1510億円を見込んでいます。
これは建機販売台数の増加が主な要因となっていますが、市場予想(QUICKコンセンサス)の861億円は下回る結果となっています。
🤷🏻♀️Why(なぜ起きたのか)
日立建機は建機販売台数の増加が263億円の増益要因になると見込んでいます。
これは欧州市場の回復や中国市場での大型ショベル需要の拡大が背景にあります。
一方で、前期まで業績を後押ししていた円安効果の剥落が141億円のマイナス要因となっています。
このような要因を総合的に勘案した結果、純利益は前期比2%増にとどまる見通しとなりました。
🤷🏻♀️When(いつ起きたのか)
この業績予想は2025年4月25日に発表されました。
予想の対象期間は2025年4月から2026年3月までの1年間です。
🤷🏻♀️Where(どこで起きたのか)
地域別の売上収益見通しでは、北米が4%減の2991億円、欧州が9%増の1744億円、中国が14%増となっています。
また、新会社を設立した中南米でも2%の増収を見込んでいます。
特に欧州は市況回復と在庫の正常化が進んでいることが好材料となっています。
🤷🏻♀️Who(誰が関係しているのか)
日立建機の塩嶋慶一郎最高財務責任者(CFO)が決算説明会で「欧州は市況が良くなり、在庫の正常化も進んできた」と話しています。
また、次期トランプ米政権による関税政策が今後の業績に影響を与える可能性があります。
🤷🏻♀️How(どのように展開しているのか)
日立建機は為替の想定レートを1ドル=145円と設定しており、前期実績(1ドル=152円60銭)よりも円高に設定しています。
これにより円安効果の剥落が見込まれています。
しかし、地域別では欧州や中国での増収を見込んでおり、北米市場の減収をカバーする形となっています。
また、トランプ次期政権による関税の影響額は300億円程度と試算していますが、現時点での業績予想には織り込んでいません。
📚 専門用語の解説:これであなたも経済通!

調整後営業利益とは?
企業の本業での実力を測るための利益指標です。
一時的な特別損益や企業買収に伴うのれん代償却などを除外した営業利益のことを指します。
日立建機の場合、国際会計基準(IFRS)を採用しているため、一過性の要因を除いた「本業の実力」を示す指標として調整後営業利益を重視しています。
QUICKコンセンサスとは?
証券アナリストによる企業業績予想の平均値のことです。
QUICK社が証券アナリストの業績予想を集計し、その平均値を算出したものです。
市場の期待値を示す指標として投資家に参考にされています。
在庫の正常化とは?
適正な在庫水準に戻ることを意味します。
コロナ禍のサプライチェーン混乱や需要変動により、多くの企業で在庫が過剰または不足していましたが、それが適切なレベルに戻りつつあることを表しています。
在庫の正常化は企業の資金効率や利益率の改善につながる重要な要素です。
のれん代とは?
企業買収の際に、買収金額が被買収企業の純資産を上回る部分のことです。
ブランド価値や将来の収益力への期待を反映したプレミアムと考えられます。
国際会計基準(IFRS)では定期的な償却は行わず、減損テストを行います。
円安効果の剥落とは?
これまで日本企業の業績を押し上げてきた円安による恩恵(海外売上の円換算額増加など)が薄れることを指します。
日立建機の場合、今期の想定為替レートを1ドル=145円と前期実績(1ドル=152円60銭)より円高に設定しているため、為替による利益押し上げ効果が弱まると予想しています。
📝 関連する経済指標や統計データ:数字で見る現状!

📊建設機械市場の世界動向(2024年)
- 世界の建設機械市場規模:約25兆円(前年比3.5%増)
- 中国市場:約5.5兆円(前年比5.2%増)
- 欧州市場:約4.8兆円(前年比2.8%増)
- 北米市場:約6.2兆円(前年比0.5%減)
- 日本市場:約2.3兆円(前年比1.2%増)
📊主要建機メーカーの世界シェア(2024年)
- キャタピラー(米):約16%
- コマツ(日):約14%
- 日立建機(日):約7.5%
- ボルボ建機(スウェーデン):約6%
- 三一重工(中):約5.5%
📊円ドル相場の推移
- 2023年4月平均:1ドル=134円
- 2024年4月平均:1ドル=152円
- 2025年4月予想:1ドル=145円(日立建機想定)
📊トランプ政権の関税政策(予定)
- 中国からの輸入品:約60%の関税
- その他すべての国からの輸入品:約10-20%の関税
- 実施時期:2025年1月以降
🔮 この記事の裏側:見えてくる真実!

日立建機の業績予想から見えてくるのは、日本の製造業が直面している「円安効果の終焉」と「地政学リスク」という二つの大きな課題です。
円安効果の終焉
まず、円安効果の剥落についてです。
日本の製造業各社は過去2年間、急激な円安によって業績を押し上げられてきました。
海外で稼いだドルやユーロが円換算で膨らみ、見かけ上の増収増益となっていたのです。
しかし、日立建機の今回の業績予想では、為替の影響が141億円の減益要因となっています。
これは「円安頼み」の経営からの脱却が求められていることを示しています。
地政学的リスク
次に注目すべきは、トランプ次期政権による関税の影響です。
日立建機は関税の影響額を300億円程度と試算していますが、これを業績予想には織り込んでいません。
なぜでしょうか?
これは関税政策の詳細がまだ不確定であることと、対策を講じる余地があるとの判断があるからではないでしょうか。
特に興味深いのは地域別の戦略です。
北米市場では4%の減収を見込む一方、欧州では9%増、中国では14%増と予測しています。
これは明らかに「北米依存からの脱却」を図る動きと読み取れます。
とりわけ中国市場での大型ショベル需要の増加を見込んでいる点は注目に値します。
中国経済の減速が叫ばれる中、なぜ日立建機は中国での増収を見込めるのでしょうか?
これには中国政府の景気刺激策が関係しています。
中国は不動産市場の不振を受けて、インフラ投資を拡大する政策に舵を切っています。
特に「新型インフラ」と呼ばれるデータセンターや5G基地局、再生可能エネルギー施設などの建設に力を入れており、これが大型ショベルの需要増につながっているのです。
また、欧州市場の好調についても単なる景気回復だけではなく、EU各国のグリーン政策の影響があります。
欧州ではグリーンディール政策のもと、再生可能エネルギー施設や環境配慮型インフラの整備が進んでおり、これが建機需要を押し上げています。
さらに見逃せないのは中南米戦略です。
日立建機は中南米に新会社を設立し、販売・サービス網の拡充に注力しています。
これは北米市場でのリスクを分散する動きであり、地政学リスクに対する「ヘッジ戦略」と言えるでしょう。
このように日立建機の業績予想の裏側には、円安効果に頼らない真の競争力強化、地政学リスクへの対応、そして新興市場の開拓という日本企業の生き残り戦略が隠されているのです。
🔭 今後の展望:未来を予測!
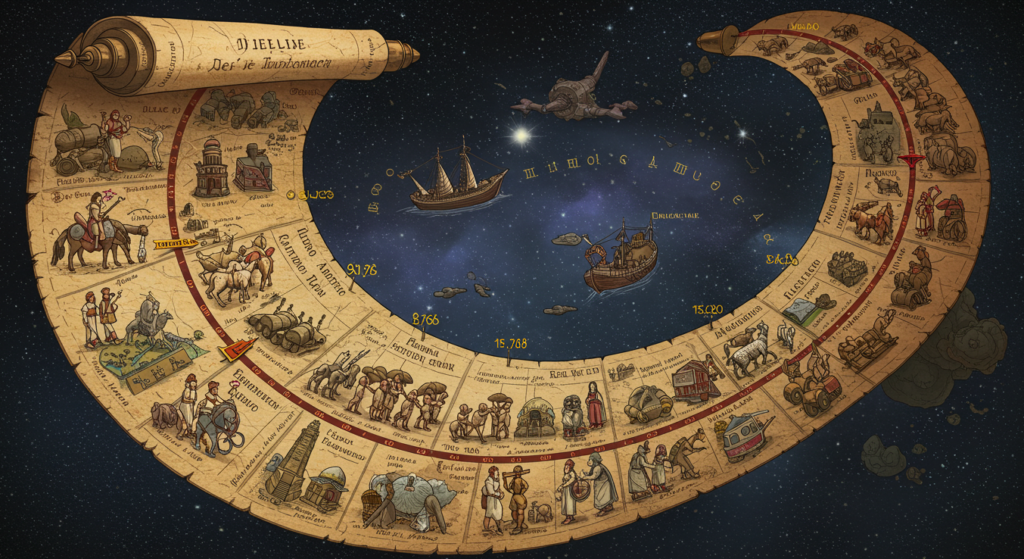
短期的な見通し(3ヶ月程度)
- 日立建機の株価変動
日立建機株は業績予想が市場予想を下回ったことで一時的に調整局面に入ります。
特に関税リスクへの懸念から、投資家の様子見姿勢が強まる可能性があります。
- 為替変動による影響
円ドル相場は145円前後で推移し、日本企業全体で「円安効果の剥落」による業績への影響が顕在化します。
第1四半期決算発表で多くの輸出企業が為替影響による減益要因を発表する展開となるでしょう。
- 地域による二極化
建機需要は地域による二極化が進みます。
欧州と中国は堅調に推移する一方、北米市場では政策の不透明感から設備投資に慎重な姿勢が広がります。
中長期的な展望(半年以降)
- グローバルサプライチェーン再編
トランプ次期政権の関税政策が実施され、グローバルサプライチェーンの再編が加速します。
日本企業は北米向け製品の生産拠点をメキシコなどに移転する動きを強めるでしょう。
- 中国で大型ショベルなどの需要拡大
中国のインフラ投資拡大政策が本格化し、大型建機の需要が一段と増加します。
特に「新型インフラ」関連の投資が拡大し、大型ショベルや特殊建機の需要が高まるでしょう。
- 電動建機への需要拡大
欧州のグリーン政策に伴い、環境配慮型の電動建機への需要が拡大します。
CO2排出規制の強化に伴い、従来のディーゼル建機から電動・水素建機へのシフトが加速するでしょう。
💹 記事から読み解く、具体的な投資戦略:今日からあなたも投資家!

📈投資戦略1:円安効果に頼らない「真の実力」を持つ企業への投資
世界的な建機メーカーである日立建機は円安効果が剥落する中でも増益を目指しています。
これは製品力や地域戦略の強さを示しています。
同様に、為替変動に左右されず、本業の競争力で成長できる企業に注目しましょう。
具体的には、高い技術力を持ち、グローバルニッチトップ企業や、海外売上比率が高くても円安に依存せずに成長している企業が候補となります。
- 投資戦略のポイント:
- PER(株価収益率)よりもPBR(株価純資産倍率)や売上高営業利益率を重視しましょう。
- 過去3年間の業績から「実質的な成長率」(為替効果を除いた成長率)を確認しましょう。
- 研究開発費比率が高く、継続的に新製品を投入している企業を選びましょう。
- 初心者へのアドバイス:
- 四季報やブルームバーグなどで「為替感応度」を確認し、数値の低い企業を選びましょう。
- 決算説明会資料で「実質ベースの成長率」に言及している企業に注目しましょう。
- いきなり大きく投資せず、少額から始めて徐々に理解を深めていきましょう。
📈投資戦略2:地政学リスクに強いグローバル分散戦略
日立建機は北米市場の減収をカバーするため、欧州、中国、中南米など多様な地域での成長を目指しています。
個人投資家も同様に、特定の国や地域に依存せず、グローバルに分散投資することでリスクを軽減できます。
特に新興国市場への投資比率を高めることで、先進国の政治リスクをヘッジしましょう。
- 投資戦略のポイント:
- 地域別の売上構成が分散している企業や、地域別ETFを組み合わせて投資しましょう。
- 「チャイナプラスワン」戦略を採用している企業に注目しましょう。
- 経済連携協定(EPA、RCEP、CPTPPなど)の恩恵を受ける企業を選びましょう。
- 初心者へのアドバイス:
- 全世界株式インデックスファンドから始めて、徐々に個別企業や地域に投資を広げましょう。
- 新興国投資は変動が大きいため、投資金額の10〜20%程度にとどめておきましょう。
- 政治リスクの高い地域への投資は、ETFなど分散型の商品を活用しましょう。
📈投資戦略3:グリーントランスフォーメーション(GX)関連銘柄への投資
日立建機の欧州市場での成長は、EU各国のグリーン政策との関連が強いです。
世界的にカーボンニュートラルへの取り組みが加速する中、環境技術や再生可能エネルギー関連企業への投資は中長期的な成長が期待できます。
特に日本企業は素材技術や省エネ技術で強みを持っており、今後の成長が見込まれます。
- 投資戦略のポイント:
- 単なる「エコ」だけでなく、経済合理性のある環境技術を持つ企業を選びましょう。
- サプライチェーン全体でのCO2削減に貢献できる企業に注目しましょう。
- 各国の環境規制強化の恩恵を受ける企業を見極めましょう。
- 初心者へのアドバイス:
- グリーン関連のテーマ型ETFから始めて、業界の動向を把握しましょう。
- 短期的なブームに乗るのではなく、5年以上の長期保有を前提に投資しましょう。
- 企業のサステナビリティレポートを読み、本気度と技術力を確認しましょう。
⚠️ 絶対やってはいけない!失敗する投資法3選:落とし穴に注意!

❌円安効果だけを見て企業を選ぶ
日立建機の事例からも分かるように、円安効果は永続的なものではありません。
単に「海外売上比率が高いから円安で儲かる」という安易な発想で投資すると、為替が反転した途端に株価が下落するリスクがあります。
実際、前年度まで円安で業績を押し上げていた多くの輸出企業が、今年度は厳しい状況に直面する可能性があります。
本質的な競争力や成長戦略を見極めずに、一時的な円安効果だけに飛びついてはいけません。
❌地政学リスクを無視した投資判断
日立建機はトランプ次期政権の関税の影響を300億円と試算しているものの、業績予想には織り込んでいません。
これは不確実性の高さを示しています。
個人投資家が米中対立や保護主義の台頭などの地政学リスクを無視して投資判断を行うと、突然の政策変更や国際情勢の変化で大きな損失を被る可能性があります。
特に「北米一辺倒」の事業戦略を持つ企業には要注意です。
日立建機のように地域分散やリスクヘッジ戦略を持たない企業への投資は慎重に行うべきでしょう。
❌業績予想だけを鵜呑みにした投資判断
日立建機の業績予想は市場予想(QUICKコンセンサス)を下回っていますが、これにはトランプ関税の影響が未反映という背景があります。
企業の公表する業績予想だけを見て投資判断を行うと、見えないリスクを見逃してしまう危険性があります。
特に国際情勢が不安定な今、企業の業績予想には「言えないリスク」や「保守的な見通し」が含まれていることがあります。
表面的な数字だけでなく、その背景や前提条件、市場環境の変化可能性などを多角的に分析しないと、期待外れの結果に終わるでしょう。
🚀 読者へのアクションポイント:さあ、一歩踏み出そう!

- 日経新聞を「逆読み」してみましょう
日経新聞の記事は基本的に「結論→理由→背景」の順で書かれています。
しかし投資の視点で読むなら、あえて「背景→理由→結論の妥当性」という逆の順序で読んでみましょう。
日立建機の記事であれば、世界経済の状況や為替動向、政治リスクなどの背景から読み解くことで、業績予想の信頼性や将来性がより明確になります。
週に1回でも構いませんから、気になる企業の記事を選んで「逆読み」する習慣をつければ、投資眼が養われていきます。
- 「円安効果」を差し引いた本当の企業力を分析しましょう
多くの日本企業が円安で見かけ上の業績を押し上げていた事実を認識し、為替効果を除いた「実質成長率」を確認する習慣をつけましょう。
具体的には、決算説明資料で「為替影響を除くと〇〇%の増減」という記述を探したり、過去の為替レートと現在の想定レートの差から概算でも構いませんので計算してみましょう。
この作業を通じて、「本当に強い企業」と「円安頼みの企業」の区別がつくようになります。
- 投資情報を「ファクト」と「オピニオン」に分けて整理しましょう
日立建機の記事でいえば、「純利益830億円の予想」はファクトですが、「欧州市場が好調」というのは会社側のオピニオンです。
投資情報を「事実」と「見解」に分けて整理することで、冷静な判断ができるようになります。
ノートに縦線を引いて左側に「ファクト」、右側に「オピニオン(自分の見解も含む)」を書き出す習慣をつけると、情報の質が高まり、投資判断の精度が上がります。
まずは週1回、関心のある企業について試してみてください。
最後に
いかがでしたか?
日立建機の業績予想一つを深掘りするだけでも、世界経済の動向や投資のヒントが多く隠されていることがお分かりいただけたと思います。
日経新聞は難しそうに見えて、実は私たちの生活や資産形成に直結する情報の宝庫なのです。
この記事をきっかけに、ぜひ経済ニュースを身近に感じ、投資への第一歩を踏み出してみてください。
もし経済や投資の基礎から体系的に学びたいと思われたら、「お金の教養講座 ![]() 」がおすすめです。
」がおすすめです。
また、株式投資をこれから始めたい方や、すでに経験はあるけれどうまくいっていない方には「株式投資の学校 ![]() 」で確かな知識を身につけてみませんか?
」で確かな知識を身につけてみませんか?
あなたの資産形成や経済リテラシー向上のお手伝いができれば幸いです。
次回の記事もどうぞお楽しみに!


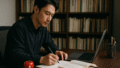


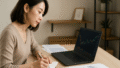

コメント