「3000億円の現金を持ってるのに、なぜもっと株主にお金を配らないの?」
毎日日経新聞を読んでいる私が思わず目を引いたこの疑問が、今、日本の株式市場で大きな波紋を広げています。
衣料品大手「しまむら」に対して投資プロ集団が仕掛けた”株主提案”というビジネスドラマ。
5年連続で最高益を更新している好業績企業なのに、なぜ「もっとお金を株主に返せ」と言われているのでしょうか?
実は、この出来事の裏側には「企業の現金保有」と「株主還元」という、あなたの資産形成にも直結する大きなヒントが隠れています。
日本企業の”お金の使い方”をめぐる攻防から、私たちが学べることは意外と多いのです。
今回は、このニュースを通じて「ROE」や「株主還元」といった投資の基本から、あなたの投資判断に役立つ具体的なポイントまで、分かりやすく解説します。
この記事の読みどころ
✅️投資のプロ集団が、好業績企業「しまむら」に対して行った過激な提案の全貌
✅️「株主提案」という、株主が会社に物申せる意外な権利について知れる
✅️なぜ業績好調なのに「もっと株主にお金を還元しろ」と言われるのか、その理由
✅️個人投資家として知っておくべき「ROE」や「株主還元」の本当の意味
✅️企業の現金保有と資本効率のジレンマから学ぶ、賢い投資判断の秘訣
ニュースの要点:3行でザックリまとめ

- マネックスのファンドが衣料品大手「しまむら」に対し、配当性向を現在の35%から60%に引き上げる株主提案を実施
- 5年連続最高益を更新するしまむらに対し、総資産の約5割を占める「過剰な現金保有」を問題視
- 提案は5月の株主総会で審議され、昨年と同様の提案は否決されている
ニュースの基本情報:5W1Hで深掘り!
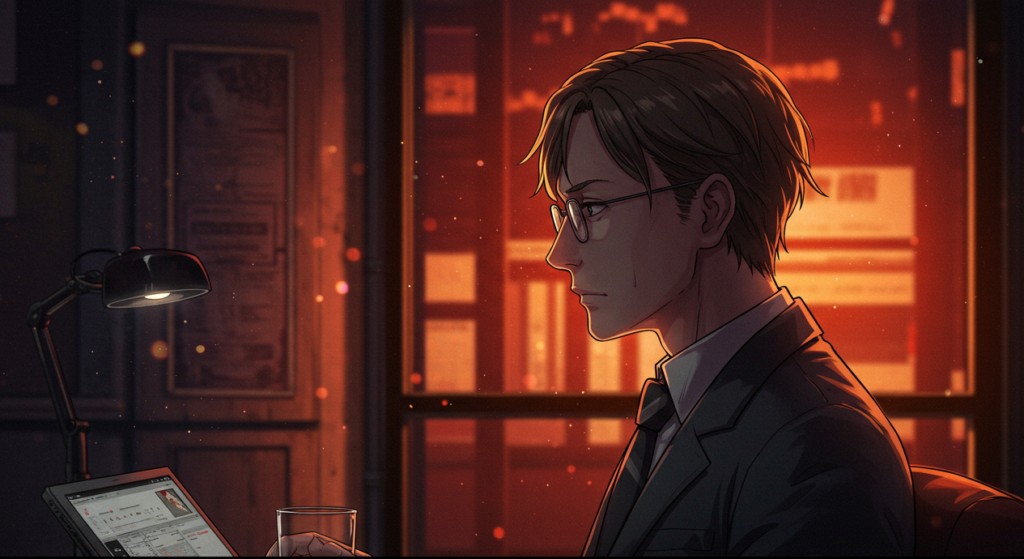
🤷🏻♀️What(何が起きたのか)
マネックスグループのファンドが、衣料品大手「しまむら」に対して株主提案を行いました。
提案の内容は大きく2つあります。
1つ目は配当性向を現在の35%から60%へと大幅に引き上げること、2つ目は160億円を上限とする自社株買いの実施です。
これらはいずれも「株主還元」と呼ばれる、会社が株主にお金を戻す方法です。
🤷🏻♀️Why(なぜ起きたのか)
提案の背景には、しまむらが「過剰な現金」を保有しているという問題意識があります。
記事によれば、しまむらの手元資金は総資産の約5割を占めており、これが「効率的に使われていない」とマネックスは判断しています。
特に、しまむら自身が掲げるROE(自己資本利益率)9%の目標達成には、3年間で800億円以上の株主還元が必要だとしていますが、現計画では450億円にとどまっているとのことです。
🤷🏻♀️When(いつ起きたのか)
株主提案は今年の株主総会(5月開催予定)で審議されます。
なお、マネックスは昨年も同様の提案を行いましたが、否決されています。
🤷🏻♀️Where(どこで起きたのか)
株主提案自体は書面で行われ、決議は株主総会の場で行われます。
しまむらは全国に店舗を展開する大手衣料品チェーンであり、郊外を中心に出店しています。
🤷🏻♀️Who(誰が関係しているのか)
この提案を行ったのはマネックスグループのファンドです。
マネックスは有名なネット証券会社を傘下に持つ投資会社で、「アクティビスト」と呼ばれる積極的に企業経営に関与する投資家の一つです。
対象となったしまむらは、2026年2月期の連結純利益が前期比2%増の428億円になる見通しで、5年連続で最高益を更新すると予想されている好業績企業です。
🤷🏻♀️How(どのように展開しているのか)
株主提案が実現するには、株主総会で過半数の賛成票を得る必要があります。
昨年は反対多数で否決されましたが、マネックスは諦めずに再度提案を行っています。
これは、しまむらの株価が業績の良さに比べて適正に評価されていないという見方に基づいています。
専門用語の解説:これであなたも経済通!

株主提案とは?
株主提案とは、会社の株主が株主総会の議題や議案として取り上げてほしい事項を会社に提案できる制度です。
単に株式を持っているだけでなく、会社の運営に対して意見を表明する方法の一つです。
提案するには一定の条件(通常は発行済み株式の1%以上を6か月以上保有するなど)を満たす必要があります。
配当性向とは?
配当性向は、会社が稼いだ純利益のうち、どれくらいの割合を株主に配当として支払うかを示す指標です。
例えば、会社が100億円の利益を出し、そのうち35億円を配当として支払う場合、配当性向は35%となります。
マネックスは、現在のしまむらの配当性向35%を60%に引き上げるよう提案しています。
自社株買いとは?
自社株買いとは、会社が市場で自社の株式を買い戻すことです。
これにより、①発行済み株式数が減少し1株あたりの価値が上がる、②買い需要が増えることで株価が上昇する、という効果が期待できます。
株主還元の一種で、配当と並んで重要な株主還元策です。
ROE(自己資本利益率)とは?
ROE(Return on Equity)は、株主が会社に投資したお金(自己資本)に対して、どれだけ効率よく利益を生み出しているかを示す指標です。
例えば、ROEが9%であれば、100円投資して9円の利益を生み出していることになります。
この数値が高いほど、資本を効率的に使って利益を出していると評価されます。
アクティビストとは?
アクティビストは、企業の経営改善や株主価値の向上を目指して積極的に経営に関与する投資家のことです。
日本では以前「物言う株主」と呼ばれ否定的なイメージがありましたが、最近では企業価値向上のための健全な対話の一環として見られることが増えています。
関連する経済指標や統計データ:数字で見る現状!

📊しまむらの財務状況
- 2026年2月期連結純利益予想:428億円(前期比2%増)
- 5年連続最高益更新の見通し
- 手元資金:総資産の約5割(業界平均よりも高水準)
- 現在の配当性向:35%
- ROE目標:9%
📊日本企業の現金保有率
日本企業の手元資金は、2024年度末で過去最高の約600兆円に達しています(日銀の資金循環統計による仮定値)。
東証プライム市場上場企業の約3割が「現金同等物」が総資産の30%を超えており、しまむらの約50%という数字は高水準ながらも、日本企業には珍しくない状況です。
📊日本と海外の配当性向比較
- 日本企業の平均配当性向:約35%(2024年度)
- 米国企業の平均配当性向:約45%(2024年度)
- 欧州企業の平均配当性向:約50%(2024年度)
日本企業は伝統的に内部留保を厚くする傾向があり、海外に比べて配当性向が低い傾向にあります。
しまむらの現在の35%という配当性向は日本の平均並みですが、マネックスが提案する60%は国際的にも高水準です。
この記事の裏側:見えてくる真実!

「過剰な現金保有」は日本企業の弱点
この株主提案の裏には、日本企業に長年指摘されてきた「過剰な現金保有」という問題があります。
多くの日本企業は「いざという時のため」に多額の現金を保有していますが、それが効率的な資本活用を妨げているという批判があるのです。
特に2008年のリーマンショックや2020年のコロナ危機を経験した企業は、危機に備えて現金を厚く保有する傾向が強まっています。
しまむらのように総資産の約5割を現金同等物で保有するケースも珍しくありません。
しかし、低金利環境が続く中、多額の現金を単に銀行に預けておくことは「機会損失」と見なされます。
その資金を成長投資や株主還元に使えば、より高いリターンを生み出せる可能性があるのです。
なぜ好業績企業が標的になるのか
一見すると、5年連続で最高益を更新するしまむらのような好業績企業になぜアクティビストが目をつけるのか不思議に思えるかもしれません。
しかし、アクティビストの視点からすれば、「業績が良いのに株価が十分に評価されていない=割安」と判断される企業こそが魅力的なターゲットなのです。
実際、日本の株式市場では「割安株」が多いと言われています。
PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などの指標を見ると、同じような業績や資産を持つ企業でも、日本企業の株価は欧米企業より低く評価されていることが多いのです。
この「バリュエーションギャップ」の原因の一つが、効率的に使われていない潤沢な現金だと指摘されています。
つまり、「この会社はもっと価値があるはずなのに、経営陣の保守的な財務政策のせいで株価が上がらない」と考えられているのです。
経営者と株主の利害の不一致
この問題の根底には、経営者と株主の間の「利害の不一致」があります。
経営者は会社の長期的な安定と成長を重視し、有事の際のリスクヘッジのために現金を厚く保有したいと考えます。
特に創業家経営の企業では、「会社を潰さない」ことが最優先されることもあります。
一方、株主、特に機関投資家は資本効率や短中期的なリターンを重視します。
彼らの立場からすれば「リスクに見合ったリターン」を得られないなら、その資金は株主に還元するべきだという考え方になります。
このような利害の不一致は、日本の株式市場においては特に顕著です。
長年、「株主を大事にする文化」が根付いてこなかった日本では、株主よりも従業員や取引先を優先する経営が一般的でした。
しかし、コーポレートガバナンス改革が進む中で、このバランスは少しずつ変化しています。
今後の展望:未来を予測!
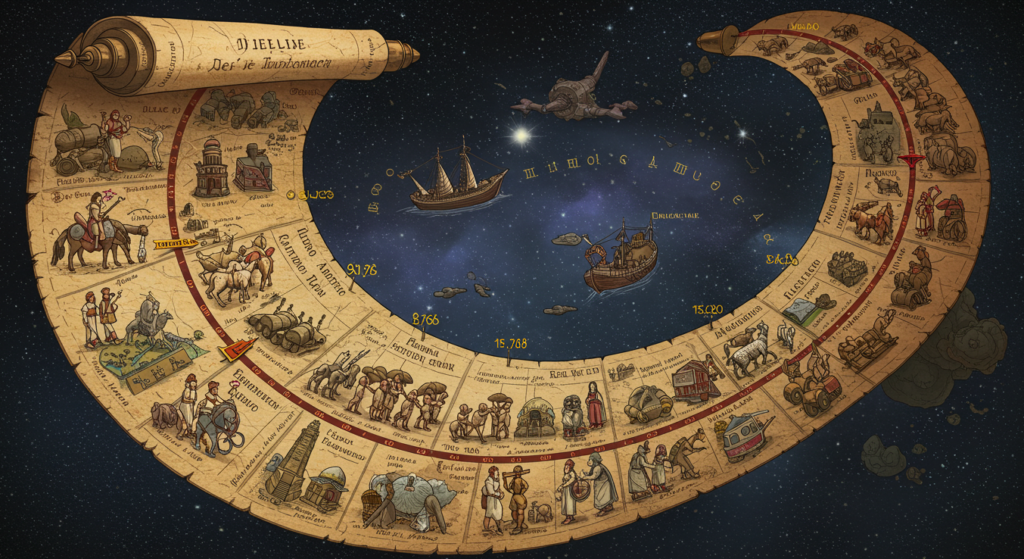
短期的な見通し(3ヶ月程度)
- 5月の株主総会で再び株主提案が否決される可能性が高い
創業家や関連会社の保有株式と、経営陣を信頼する個人株主の票を合わせると、過半数を超える可能性が高いです。
特に日本の個人株主は経営陣の判断を尊重する傾向があります。
- 否決されても、しまむらが譲歩案を出す可能性あり
完全な否決でも、部分的に株主還元を強化するなど、アクティビストの要求に一部応える可能性があります。
実際、昨年の株主提案後、しまむらは配当を若干増やしています。
- しまむらの株価は短期的には変動するも、業績の堅調さから底堅く推移
株主提案の行方によって株価は変動しますが、基本的にはしまむらの業績が堅調なため、極端な下落リスクは低いと思われます。
中長期的な展望(半年以降)
- 日本企業全体で株主還元強化の流れが継続
東証がコーポレートガバナンス改革を推進する中、PBR1倍割れ(株価が純資産を下回る)企業などを中心に、株主還元強化の流れは続くでしょう。
- 海外投資家の日本株への関心増加
日本企業の株主還元強化や、円安傾向などを背景に、海外投資家の日本株への投資意欲が高まる可能性があります。
特に割安で株主還元に積極的な企業には注目が集まるでしょう。
- アクティビストの活動がさらに活発化
日本企業の「割安さ」と「現金保有の多さ」という特徴は、アクティビストにとって魅力的です。
しまむらのケースに限らず、他の企業でも同様の動きが増えていくでしょう。
記事から読み解く、具体的な投資戦略:今日からあなたも投資家!

📈投資戦略1:「アクティビスト注目銘柄」への投資
アクティビストが注目する企業は、「割安」かつ「改善余地がある」と判断された企業です。
特に、PBR1倍割れで現金比率が高い企業は、潜在的なターゲットとなる可能性があります。
具体的には、財務諸表で「現金及び現金同等物」が総資産に占める割合が30%を超え、かつPBRが1倍前後の企業をチェックしてみましょう。
- 投資戦略のポイント:
- 業績は堅調だが株価が割安な企業を探しましょう。
- 総資産に占める現金比率が高い企業に注目しましょう。
- アクティビストの動きがニュースになった直後は一時的に株価が上昇することが多いので、タイミングを見計らって投資しましょう。
- 初心者へのアドバイス:
- いきなり個別銘柄に投資するのではなく、まずは投資信託や ETF から始めましょう。
- 投資判断は一つの指標だけでなく、複数の角度から行いましょう。
- 投資前に最低限の財務諸表の読み方を勉強しましょう。
📈投資戦略2:「高ROE・高配当銘柄」への投資
ROEが高く、かつ配当性向も高い企業は、効率的な経営と株主還元の両立を実現している優良企業の可能性があります。
具体的には、ROE8%以上、配当性向40%以上の銘柄をスクリーニングしてみましょう。
これらの企業は、安定したキャッシュフローを生み出しつつ、株主にもしっかりリターンを還元しています。
- 投資戦略のポイント:
- ROEが継続的に高い企業を選びましょう(一時的な高ROEは要注意です)。
- 配当の安定性・成長性もチェックしましょう。
- 業績の安定性も重要な判断基準になります。
- 初心者へのアドバイス:
- 高配当だけを見て投資すると失敗することがあるので、会社の業績や財務状況もチェックしましょう。
- 長期保有を前提に銘柄を選びましょう。
- 複数の銘柄に分散投資して、リスクを抑えましょう。
📈投資戦略3:「株主還元強化の動きがある企業」への投資
自社株買いの発表や増配など、株主還元強化の動きがある企業は、短期的に株価が上昇することが多いです。
特に、従来保守的だった企業が株主還元に積極的になるケースは要注意です。
企業の決算発表や中期経営計画の更新時期などをチェックして、株主還元方針の変化を見逃さないようにしましょう。
- 投資戦略のポイント:
- 株主還元に関する重要な発表は、決算発表や株主総会前後に行われることが多いので、この時期に注目しましょう。
- 特に「初めての自社株買い」や「大幅な増配」などは株価に好影響を与えることが多いです。
- 株主還元強化の理由(業績好調か、アクティビスト対応か)も判断材料になります。
- 初心者へのアドバイス:
- 会社のIRサイトをチェックして、株主還元方針を確認する習慣をつけましょう。
- 株主優待目当ての投資は、長期的なリターンには結びつかないことがあるので注意しましょう。
- 定期的に投資先企業の状況をチェックする習慣をつけましょう。
絶対やってはいけない!失敗する投資法3選:落とし穴に注意!

❌「現金保有率だけで銘柄を選ぶ」
今回のしまむらの例では、「現金保有率が高い=非効率的経営」という図式で語られていますが、実はこれは業種や企業の状況によって大きく異なります。
例えば、景気変動の影響を受けやすい業種では、多めの現金保有が安全策として合理的なこともあります。
また、大きな設備投資や買収を控えている場合も、現金を厚く持っている理由があるのです。
現金保有率だけを見て「効率が悪い」と判断するのは危険です。
❌「アクティビストが関与したから即投資する」
アクティビストが関与すると株価が上がるというパターンを期待して投資するのは危険です。
マネックスとしまむらの例でも、昨年の株主提案は否決されています。
アクティビストの提案が会社の状況に適合しているか、実現可能性はあるか、経営陣の対応はどうかなど、総合的に判断する必要があります。
単に「アクティビストが関与した」という理由だけで投資を決めるのは避けましょう。
❌「企業の保守的な財務方針を全否定する」
日本企業の保守的な財務方針(多額の現金保有など)は、短期的には非効率に見えるかもしれません。
しかし、これが長期的な安定性につながり、結果的に持続可能な成長を実現している面もあります。
例えば、2008年のリーマンショックや2020年のコロナ危機では、手元資金が潤沢な企業は危機を乗り越え、むしろ苦境にある企業を買収するなどのチャンスを得た例もあります。
企業の保守的な姿勢を単に「古い」と決めつけず、その戦略の意味を理解することが重要です。
読者へのアクションポイント:さあ、一歩踏み出そう!

- 自分の保有株(または興味のある企業)の「現金比率」と「ROE」をチェックしてみましょう
今回の記事を通じて、企業の財務効率を判断する上で「現金比率」と「ROE」が重要な指標であることがわかりました。
自分が保有している株式や、興味のある企業について、この2つの指標を調べてみましょう。
総資産に占める現金の割合が高く、ROEが低い企業は、今後株主からの圧力が高まる可能性があります。
- 次の決算発表では「株主還元方針」に注目しましょう
企業の決算発表では、業績の数字だけでなく、配当方針や自社株買いなどの「株主還元方針」もチェックしましょう。
特に「配当性向」という指標に注目し、その企業が利益の何割を株主に還元する方針なのかを理解することが重要です。
最近では多くの企業が株主還元に積極的になっていますが、業種や企業によって大きな差があります。
- 企業のIR情報を定期的にチェックする習慣をつけましょう
投資判断の質を高めるには、定期的に企業のIR(投資家向け広報)情報をチェックする習慣が重要です。
決算短信や有価証券報告書だけでなく、会社が開催する株主総会や決算説明会の資料も貴重な情報源になります。
特に経営者が「株主還元」についてどのような考え方を持っているかを理解することで、将来の投資判断に役立てることができます。
最後に
しまむらへの株主提案から見えてきたのは、日本企業と株主の関係が大きく変わりつつある新時代の流れです。
「ただ現金を貯め込むだけ」ではなく、「効率的に資金を活用する」企業が評価される時代になってきました。
私自身、日経新聞を読み込んで株式投資をしてきた経験から言えるのは、知識が資産を守り、増やす最大の武器になるということ。
初めは難しく感じる経済用語や企業分析も、一歩踏み出せば誰にでも理解できるようになります。
まずは「お金の教養講座」で資産運用の基本を学んでみませんか?
また、具体的な株式投資の手法を身につけたい方には「株式投資スクール」がおすすめです。
日経新聞の記事も、学んだ知識があれば難しい用語も理解できるようになり、あなたの大切な資産を育てる強力な味方になります。
楽しみながら学び、自分の未来に投資する。
その第一歩を、今日から踏み出してみませんか?


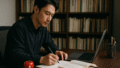


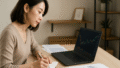


コメント